はじめに
膝の痛みに悩んでおられる方は本当にたくさんおられます。今この記事にたどり着いてくださったあなたも日ごろ膝の痛みに悩んでおられこのサイトに来てくださったのだと思います。
膝の関節は頭や両腕に加え体幹部そして太ももの重みを一手に引き受けてくれておりストレスがかかりやすい関節です。
どのようにすれば膝の痛みから開放されるかを人体の解剖学的な視点から考えていき、具体的に痛みを解消する方法についてお伝えしたいと思います。

そもそも膝の構造ってどんなふうになってるの?
まずは膝の構造がどんなふうになっているのかを画像を通して一緒に見ていきたいと思います。膝の構造を知ることでどこに痛みがでてしまうのかを知ることができ、その原因を予測したり痛みを改善しやすくするためです。
骨

膝関節は大腿骨と膝のお皿と呼ばれる膝蓋骨(しつがいこつ)そして脛骨(けいこつ)から構成されています。骨の周りを覆っている骨膜には痛みを感じる受容器が存在します。
半月板
次は半月板です。これは膝関節の中に存在し骨にかかる負担を緩衝してくれる役割にくわえ関節の安定性保持や関節の動きをよくするなどの機能を果たしてくれています。
この半月板には痛みを感じる受容器は存在しません。
膝半月版は脛骨の内・外関節面にあって半月状の形をしています。正常の半月板は白色をしていてその表面はつるつるです。しかし高齢になると関節軟骨の表面は徐々に黄色に変化します。
半月板の周りは厚く関節包とくっついています。
内側半月板


外側半月板


関節軟骨
この関節軟骨にも痛み受容器は存在しません。しかしこの軟骨が磨り減って軟骨の下の骨膜まで突き抜けると痛みを感じます。厚さは大人の膝関節では2~4mm程度です。

この関節軟骨が損傷されても軟骨が自然に修復さえることはありません。ただ損傷が軟骨を突きぬけ軟骨の下の骨にまで達するような軟骨損傷では修復されるが損傷する前のもとの軟骨となることはない。
靭帯(じんたい)
靭帯には痛み受容器が存在します。したがって何らかの原因で靭帯にストレスが加わると痛みの原因となります。
膝周囲の靭帯はとても強靭で関節の安定性をたかめてくれています。
外側縦膝蓋支帯・外側横膝蓋支帯・膝蓋靱帯・内側縦膝蓋支帯・内側横膝蓋支帯・内側縦膝蓋支帯

腸脛靭帯

膝関節包
関節包はコラーゲン線維束からなり長軸方向に引っ張られ、力を緩めると元の長さに戻ります。このようにばねのような弾性が膝の動きを柔軟にしてくれています。

筋肉
筋肉の基本的な役割は筋肉が収縮することにより力を生み出すことです。ちなみに筋肉は体重の約40%を閉める組織になります。
これは皆さん良く分かっておられると思いますが筋肉には痛みを感じる受容器が存在します。
大腿直筋・外側広筋・内側広筋・(中間広筋)・縫工筋

前脛骨筋・腓骨筋・腓腹筋・ヒラメ筋

膝の痛みはどうして起こるの?
これから膝関節に痛みが生じる原因について考えていきたいと思います。
筋肉などの柔らかい組織にストレスが加わることで生じる痛み
膝に痛みを感じてしまうきっかけはたくさんあります。たとえば・・・
・学生時代にスポーツをやっておられた方はそのときのスポーツで膝を痛めたことがきっかけで膝に痛みが出はじめた痛み
・足の裏を怪我されたことで歩き方が変わったことで膝にではじめた痛み
・また年齢とともにだんだん膝が伸びにくくなってしまうことでではじめた痛み
上記をはじめとしてきっかけは様々です。
これらの痛みの原因を大別すると
・膝にかかるストレスが限局して生じることによって筋肉や靭帯など柔らかい組織にストレスがかかることにより生じる痛み
・膝関節の軟骨が磨り減ってしまい関節下骨まで傷害されることによって生じる痛み
に大別できます。
体重が身長に対して重すぎませんか?BMIってなに?
体重が重すぎるとそれだけ膝にかかる負担は大きくなります。
そこで自分の体重が身長に対して過剰に重くないかを判断する計算式をこれからご紹介します。
計算式は次のとおりです。
BMI=体重(kg) ÷ <身長(m) X 身長(m)>
身長と体重から人の肥満度をしめす体格指数を算出する計算式になります。これをBMI(body mass index)とよびます。
この計算式は世界中で用いられていますが基準は国によって異なります。
日本では22を標準体重。18.5未満を低体重、25以上を肥満としています。
たとえば自分の身長が170cmだとすると1.7×1.7×22の計算式で自分の身長に対する標準体重がわかりますので身長のところにご自分の身長(メートル)を当てはめて計算してみてください。
これらを計算することによって自身のBMIと標準体重との差から客観的に自分の体重が重すぎるのかそうでないのかを知ることができるのです。
膝の痛みを改善する簡単な運動を紹介しましょう
運動することをやめた方が良いとき(禁忌)
実際にリラクセーションや運動に入っていく前にまずは運動したりせず何よりも安静にしておくことが最重要となる時期の特徴についてお伝えします。
皆さんもケガをされた直後に赤くなり、腫れあがって(はれて)、痛くなって熱をもったという経験をされたことがあるかと思います。このような生体反応を炎症と呼びます。
炎症がおこるとサブスタンスP、ブラジキニン、ケモカインなどの体内物質が放出されると血管の内側に隙間ができて水分が血管の外に血管内から逃げていってしまいます。そのためケガをした直後は腫れ上がるのです。
この時期には動かしたりせずRICE処置を行ってください。
このRICE処置とは何かというと
・Rest(安静):ケガをした直後は体の組織を修復する作業を行っていますがこの時期に動かしてしまうと修復が遅れてしまうことになります。受傷した直後は何よりも安静が大切です。
・Iceing(アイシング 冷却):痛みが強く熱を持っているような状況ではアイスノンなどで冷やしてあげましょう。膝でも特に痛みが出ている部分を冷やしてあげることで痛みが和らぎます。
・Compression(圧迫):これはなかなか慣れない方は難しい場合もあると思いますが弾性包帯などで軽く圧迫してあげます。圧迫してあげることで腫れなどをコントロールしてあげることができます。
・Elevation(挙上):枕やクッションなどを利用しできるだけ膝などの痛い患部を高い位置に置いてあげましょう。ポイントは心臓よりも高くすることです。
これらの英文字の頭文字を取ったものがRICEです。
どんな動作のときに痛みが出るのかを実際に動いて確認しましょう(評価)
膝が痛いといっても膝の痛みがいつどんな時に出ているのかまではなかなか把握していないものです。そこでいつ・どんな時に痛みがでるのかを実際に確認してみましょう。
例えば立ち上がったときや歩き始めなどどんな動作で膝に痛みがでるかを知ることです。あとで実際に痛みが改善したかを確認していただきますので、ここでしっかりと膝の痛みがいつ・どんな動作でるのかを評価しておいてください。
リラクゼーション(ふともも・ふくらはぎ)
膝周りの組織が硬い状態でいきなりスクワットなどをしようと思ってもふくらはぎや太ももがつっぱったような硬いままだと逆に膝関節にストレスを与えるスクワットになってしまいます。
そこでまずはその硬いところを柔らかくしてあげる必要があります。ふくらはぎや太ももをさすったり、マッサージするだけでも何もしないまま運動するよりはいいのですが、より効果の出やすい方法をお伝えしたいと思います。
皮膚の動きが悪い場所を特定する
実際に膝周辺の太ももやふくらはぎに動きの悪いところがないか触ってみましょう。痛くない方の足の同じ部位を触ると動きの違いがわかりやすいかと思います。

皮膚の動きの悪い方向を特定する
膝の痛みを感じる部位は体の深部にある筋肉だけでなく同時に皮膚の表面も硬くなっていることがほとんどです。
①まずは先ほど特定した膝周囲の動きの悪い部分に手を当ててみてください。
②動きの悪くない部分もしくは反対側の同じ部分に手を当ててみてください。皮膚の動きやすさ動かしやすさに違い(左右差なども)を感じられるのではないでしょうか?
③動きの悪い部分(先ほど動きが悪い場所を感じ取れなかった場合は痛みを感じる場所の皮膚表面)を手のひら全体で動かします。

この時のポイントとしては、時計をイメージして・・・。
・時計の中心→12時へ、
・中心→1時の方向へ、
・中心から2時、3時…10時…
といった具合に時計の中心から時計を思い浮かべながら時計の中心から12の方向へ時計を一周回すように手のひら全体で滑らせます。動かしていく中で動きにくいなと感じる方向がわかりましたでしょうか?
④その動きにくいなと感じた方向に皮膚を動かし10秒ほど止めておきます。そして皮膚を緩めてもういち度動かしてみましょう。
先ほどよりも硬さを感じずに動かせるようになったでしょうか?
⑤動くようになったら次の場所に移ってください。
皮膚を縮める
次に新しい治療アイデアに入っていきます。下の図をご参照ください。

これは太ももの皮膚を自分自身の手で寄せ集めて縮めている様子を表した図になります。皮膚表面を手で軽くつかむようにして皮膚を寄せ集めます。特に痛みを感じ始めて間もないころはこの皮膚を縮める方法が非常に効果的です。
それでは動きの悪い方向を特定できたら(はっきりわからなくても多分この方向かな・・・?で大丈夫ですよ。)
①これまでは手のひら全体で触れていたのを指先を軽く前げて先ほど特定した動きの悪い部位を触れましょう。
②そして10秒ほど皮膚を指先で軽くつまむように(引っ掛けるように)縮めます。10秒ほど引っ張ったら一度ゆるめます。
③そして再び先ほどの同じ部分を再度縮めみましょう。先ほど10秒間ほどかけて皮膚をストレッチする前と比べて明らかにやわらかくなっているのではないでしょうか?これが皮膚ストレッチの効果です。
この手順で動きの悪い方向を感じたら指先を軽くまげて引っ張る作業を繰り返してみましょう。何度か繰り返した頃にはあなたの太ももやふくらはぎはかなりリラックスしてガンコな硬さからは、かなり解放されているのではないでしょうか。
皮膚をねじる
最後に皮膚の表面を軽くねじるようにして動きをだす方法をご紹介していきます。下の図を参考にしながら実際にあなたもやってみましょう。

①皮膚の動きにくさ、もしくは痛みを感じる部位に指先で軽い圧を加えながら、ネジを回す時の要領で時計回りそして反時計回り周りの方向に太ももやふくらはぎの皮膚を動かしてみてください。
②この時のポイントとしては動きやすい方向(時計回り・反時計回り)に動かすことがとても重要になります。
③手のひら全体で皮膚を動かした時のように10秒前後皮膚をねじった状態で皮膚をストレッチします。
そして10秒ほどストレッチしたら手をゆるめてみましょう。そして先ほどと比べて柔らかくなっているかを確認してみます。
④仮にもし柔らかくなっていなかったらもう一度チャレンジしてみましょう。もしも柔らかくなっていたら他に皮膚の硬さのある部分を探してみてネジまわしをイメージしながら自分で治療していきましょう。
ここまでは皮膚ストレッチの様々なバリエーションについてお伝えしてきました。
ひと言に皮膚のストレッチといっても
・動きの悪い部分を探す。
・皮膚の動きの悪い方向を特定しその方向に動かす、動きの悪い部位を縮める、ネジる。
といった方法があることをわかっていただけたのではないでしょうか?
やり方は非常にシンプルなのですが、自分の膝の痛みとしっかりと向き合いながら、自分の手で動きにくい部分を感じとってあげることが、とても大切になっていきます。
ふとももの筋肉のストレッチ
それでは太ももの筋肉のストレッチについてお話します。
①先ほどご紹介した筋肉の解剖を思い出していただき絵のようにしっかりと筋肉をつかみます。
②そして筋肉の走行に対して垂直に動かし動きの悪い(硬い)方向を特定できたら動きの悪い方向に痛みのない範囲で動かし10秒ほど止めます。
③10秒ほどしたら再び戻してもう一度先ほど動きの悪かった方向に動かします。するとどうでしょうか?先ほどよりもスムーズに動きませんか?
④動いたことを確認したら次のところに移り再び①からはじめます。

ふくらはぎの筋肉のストレッチ
太もものストレッチと同じ要領でふくらはぎの筋肉もストレッチしていきましょう。

私が理学療法士として患者さんを治療する時には、必ずこの「筋肉と皮膚を分けて考え治療する」ということを実践しています。それは筋肉の硬さと皮膚の硬さを同時にストレッチして柔らかくしようとしても、なかなか同時に柔軟性を出してあげることは難しいためです。
膝のお皿を動かしてみよう!
膝のお皿(膝蓋骨)の動きが悪くなると膝の痛みの原因になりやすいです。したがってここでは膝のお皿の動きを作るためのストレッチについてご紹介したいと思います。
①下の図のように足を伸ばして座ってみましょう。このとき足の力はしっかりと抜いてください。(このような姿勢をとることが難しければ膝を伸ばせるベッドソファーなどを利用するのも良いでしょう。)

②そして膝のお皿を両方の親指と人差し指でしっかりと把持して上下・左右・斜めといった具合に動かしてこれ以上動かないというところの少し手前で10秒程度とめてストレッチしましょう。

*膝のお皿のストレッチも動きが悪い方向に動かすのが基本にはなるのですが、痛みを感じる方向には動かさず痛みを感じにくい方向から動かすようにしてください。
筋力トレーニング・動作練習
スクワット
それではよりダイナミックな運動に移ります。このスクワットのポイントとしては下の図で表しているように膝が外を向いたり内側を向いたりさせないことが何よりも重要です。

もう少し細かいことを言えば上の真ん中の図の様に膝を曲げた時に足趾の2番目(足の人差し指)と膝のお皿が同じ線上にあるようにすることが大切です。
どうしてもお皿と第2足趾を同一線上に持ってこれない場合はできるだけで大丈夫です。
実際にこのスクワットをやってみて何か太ももやふくらはぎにつっぱり感を感じた場合はもういち度前のステップに戻ってそのつっぱりを感じた部分をリラクセーションしてください。
フォワードレンジ
次はフォワードレンジといって下の図のように片脚を前にだして前に出した方の足を曲げ伸ばしするトレーニングです。


この時のポイントとしてはスクワットの時と同じで前に出した方の膝が内を向いたり外を向いたりしないように足趾と膝をまっすぐ前に向けることがポイントになります。
①前に出した方の膝はあまり無理せず曲げれるところまで曲げて伸ばしてください。
②膝を曲げたところで一度止めて保持してください。
③そこからゆっくりと膝を伸ばして止めて・・・といった具合に運動してください。
*このときのポイントとしては膝を痛みが無い範囲で伸ばすことです。
効果を感じてみよう!(再評価)
先ほど痛みが出ると確認した動作をもういち度やってみて痛みの程度が変化したかを感じてみましょう。
まとめ
膝関節の構造を知っていただき膝の痛みに対する皮膚ストレッチの方法と実際の運動の仕方についてお伝えしてきました。実際にお伝えした手順でやっていただけたならばあなたの膝の痛みは改善したのではないかと思います。
Activity is the best medicine
これは運動は最大の薬という意味の英語です。この文のように痛みがある状態で放っておくのではなく少しずつ良い方法をもって動かしてあげることは非常に大切なことです。
しかしケガをしてそれほど経っておらず、熱をもったり腫れていて炎症期にあるときは症状を悪化させる危険性が高いため皮膚のストレッチや運動は行わないようくれぐれも注意してください。
この記事を通して皆さんの膝の痛みが早く改善されればこれほどうれしいことはありません!












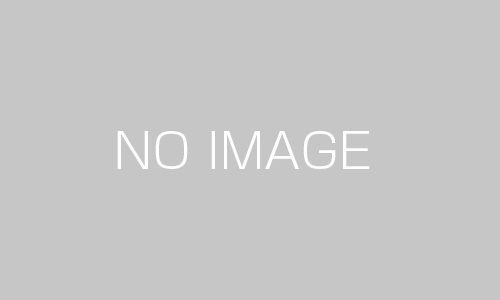




またまた、参考にさせて頂きます!
いつもコメントくださりありがとうございます。
またご感想などよろしくお願いします!